 トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて |
ENGLISH
トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて |
ENGLISH
 トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて |
ENGLISH
トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて |
ENGLISH
21世紀の検定 としての、 相関係数の検定 を、このページで整理します。
相関係数の検定では、相関係数を、検定対象、効果量、寄与率で共通して使います。 共通しているので、分けて説明する必要がないのですが、他の検定の準備として、他の検定と同じ分け方で、このページは説明しています。
相関係数は、2つの変数の共分散を、2つの変数の標準偏差の積で割った量です。
相関係数の信頼区間は、以下になります。
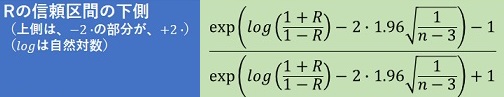
実務では、信頼区間として知りたいのは、相関係数がどのくらいまで低い可能性があるのかなので、 以下では、信頼区間の下側について説明します。 このページの他の信頼区間についても同様です。
相関係数の信頼区間の下側の具体的な計算は、以下になります。
R1セルに相関係数、N1セルにサンプル数を入力しておくと、以下の関数はコピペで使えます。
r1 : 相関係数
n1 : サンプル数
= ( EXP(LN( (1+r1)/(1-r1) ) -2*1.96/SQRT(n1-3) ) -1) / ( EXP(LN( (1+r1)/(1-r1) ) -2*1.96/SQRT(n1-3) ) +1)
=T.DIST.2T((ABS(r1)*SQRT(n1-2)/SQRT(1-r1^2)), n1-2)
P値の信頼区間 は、p値を求める式に、相関係数の信頼区間の下側を入れる案を、さしあたって考えてみました。
相関係数の信頼区間の下側をR2セルに入力しておくと、以下の関数はコピペで使えます。
=T.DIST.2T((ABS(r2)*SQRT(n1-2)/SQRT(1-r2^2)), n1-2)
相関係数の検定の場合、 効果量 は相関係数です。
検定対象の信頼区間は、そのまま 効果量の信頼区間 にもなります。
相関係数の2乗は、 寄与率 としての意味を持っています。
相関係数をR1セルに入力しておくと、以下の関数はコピペで使えます。
=r1^2
寄与率の信頼区間(上側)です。 寄与率を求める式に、相関係数の信頼区間の下側を入れます。
相関係数の信頼区間の下側をR2セルに入力しておくと、以下の関数はコピペで使えます。
=r2^2
相関係数の検定のo値 のページにまとめています。
「相関係数」 BellCurve
https://bellcurve.jp/statistics/course/9591.html?srsltid=AfmBOoqa6-P_7C2gdCj3YsVpvE8wu01RHpbLPdc1Z55IUaZHTfOi-xYu
相関係数について、検定や、信頼区間が示されています。
順路


 次は
相関係数の検定のo値
次は
相関係数の検定のo値

