 トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて |
ENGLISH
トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて |
ENGLISH
 トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて |
ENGLISH
トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて |
ENGLISH
21世紀の検定 としての、 対応のある平均値の差の検定 を、このページで整理します。
対応のある検定
の復習になります。
対応のある検定
は、
平均値の差の検定
の一種で、下のようなデータがあった時に、Z1とZ2という2つのグループの、それぞれの平均値に差があるかを調べます。
その時に、データの各行は対応があるとします。
例えば、「各行は同一人物のデータ」といった場合です。
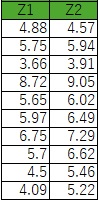
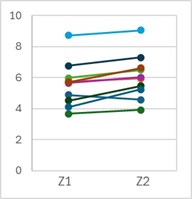
対応のある検定
では、「Z2 - Z1」というように、各行の差Yを計算します。
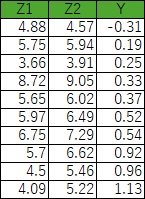
この後、 対応のある検定 では、 平均値の検定 をします。 Z2がZ1よりも大きければ、Z2-Z1のほとんどは、0よりも大きくなるはずなので、 「Z2-Z1の平均値は、0よりも大きいと言えるか?」という問題として扱います。
同様にして、対応のある平均値の差の検定のo値では、この後は、 21世紀の、平均値の検定 の手順になります。
1つのグループの平均値と基準値の差です。 基準値を0にして、「平均値は、0か?」という使い方が多いです。
平均値の差の検定では、信頼区間が下記の式になっています。
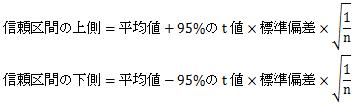
平均値差の信頼区間の下側の具体的な計算は、以下になります。
D1セルに平均値の差、N1セルにサンプル数、S1セルに標準偏差、を入力しておくと、以下の関数はコピペで使えます。
d1 : 平均値 - 基準値
n1 : サンプル数
s1 : 標準偏差
=d1 - T.INV.2T(0.05,n1) * s1 / SQRT(n1)
以下のどちらの関数でも、同じp値が求まります。
=T.DIST.2T(d1/ s1 / SQRT(n1)), n1)
P値の信頼区間 は、p値を求める式に、平均値の信頼区間の下側を入れます。
平均値の信頼区間の下側をD2セルに入力しておくと、以下の関数はコピペで使えます。
=T.DIST.2T(d2/ s1 / SQRT(n1)), n1)
平均値の検定の効果量は、平均値と基準値の差を、標準偏差で割った式です。
=d1 / s1
効果量の信頼区間
は、平均値の信頼区間との対応から、以下で良いと筆者は考えています。

=d1 / s1 - T.INV.2T(0.05,n1) / SQRT(n1)
寄与率 は、 平均値の差の検定の寄与率 の応用で、以下のようにして計算すれば良いと、筆者は考えています。

元のデータをX1という変数にして、平均値を引いたデータX0を作ります。
X0の平均値は0になります。
標準偏差は、変わらないです。

データを一列に並べて、新たにXという変数を作り、Xの値でY1とY0を区別できるようにします。
ここまで準備できると、ここからは、 平均値の差の検定の寄与率 と基本的に同じです。 相関係数rを求めます。
寄与率は、相関係数の二乗です。
=r1^2
近似曲線の機能を使うと、相関係数の二乗をグラフの中に、表示させることもできます。

o値の信頼区間(上側)です。 相関係数の信頼区間 を使います。
=( ( EXP(LN( (1+R1)/(1-R1) ) -2*1.96/SQRT(n1-3) ) -1) / ( EXP(LN( (1+R1)/(1-R1) ) -2*1.96/SQRT(n1-3) ) +1) )^2
平均値の検定のo値 のページにまとめています。
順路


 次は
21世紀の、分散の比の検定
次は
21世紀の、分散の比の検定

