 トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて | ENGLISH
トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて | ENGLISH
 トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて | ENGLISH
トップページ |
ひとつ上のページ |
目次ページ |
このサイトについて | ENGLISH
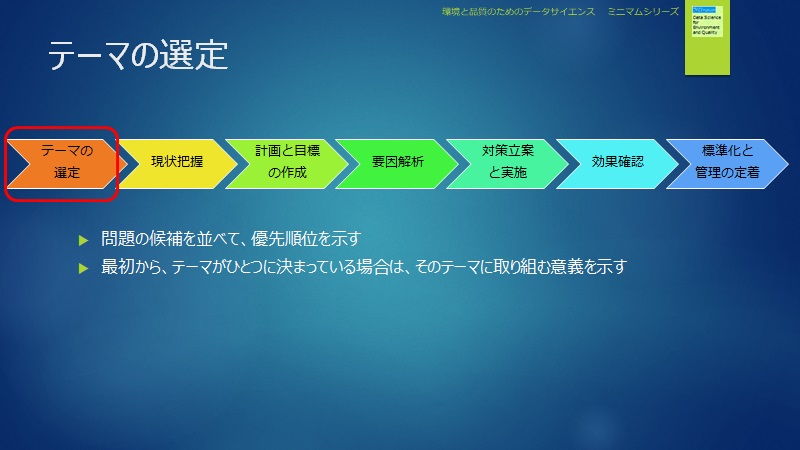
仕事の進め方には、「マルチタスク(同時並行)」という進め方もありますが、
問題解決の手順
では、「優先度を決めて、順番にやる」という考え方で作られています。
活動の背景によって、「会社としての優先順」が良いこともありますし、「メンバがやりたいことの順(多数決)」で決めることもあります。
「テーマの選定」という作業を文字通り実施するのは、 小集団活動 や、実務も兼ねた社内教育の中、あるいは「この手法を実務の中で試したい」といった場合です。
しかし、現実には、選べる状況ではなく、「上司からの指示」、「お客さんに報告しなければならない」、 といった理由で「やるしかない」ということの方が多いと思います。 こうした場合は、「やるしかない」と”会社が”考える理由や、テーマの価値や背景を考える段階にすると良いです。 視野が広がり、対策を考える時に役立つこともあります。
順路


 次は
現状把握と要因解析の区別
次は
現状把握と要因解析の区別

